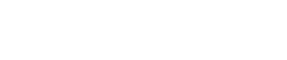硬質フェルトボードが熱い理由:環境・機能・施工性を徹底解説
2025.10.07

はじめに:注目素材としての台頭と現場体感
硬質フェルトボードは、ここ数年で展示会や建材・工業製品の分野で急速に露出が増えてきました。
たとえば、2025年6月に東京ビッグサイトで開催された オルガテック東京2025 では、吸音材や調音パネルにフェルトボードが数多く主ってされており、従来の吸音パネルに代わる「環境配慮型素材」として存在感を示していました。
私自身もフェルトボードの施工現場に立つ機会が増えており、特に「反りにくさ」「加工性」「意匠性」の面で、他の防音材料にない魅力を感じています。
また最近では、廃棄繊維を再利用したリサイクルフェルト や、耐熱性・高強度のアラミド繊維フェルト(ケブラー®、ザイロン®など) も市場に増えてきており、吸音用途だけでなく、緩衝材・輸送材・耐熱パッキン・構造補助材など多面的な展開が進んでいます。
本記事では、吸音材としての特徴に加え、
- 緩衝・クッション用途
- ピンボード(掲示板)やコルク代替用途
- 高耐熱・高強度フェルト(ケブラー®・ザイロン®など)
を整理し、メリット・デメリットを含めた包括的な解説を行います。
硬質フェルトボードとは何か?構成と素材
まず、硬質フェルトボードとはどのようなものかを整理しておきましょう。
基本構成・素材
- 多くは ポリエステル系(PET 等)繊維 を原料とし、高密度に圧縮・成形して板材化したフェルト(不織布状繊維材)です。
- 繊維同士を接着、又は熱融着させるか、表面処理(コーティングなど)を併用して剛性を出す方式が一般的。
- 製品によっては再生 PET 繊維を一部使用し、環境負荷を抑えたものもあります。たとえば、ドリックス社の「Felmenon(フェルメノン)」シリーズでは、再生 PET 素材を約 50%活用している旨の記述があります。
- 厚さは数ミリ〜数十ミリ程度、色・表面仕上げ・模様(面取り、凸凹パターンなど)を付加できるバリエーションも豊富。
- 吸音性能を持たせることを主目的としつつ、意匠性を兼ねた建材・インテリアパネルとして展開されています。
こうした性質が組み合わさって、吸音・調音・内装材として魅力的な選択肢となってきています。

吸音性能・音響特性
- 硬質フェルトボードは、中高域(おおよそ1,000〜5,000 Hz 前後) の音波を内部繊維が吸収する能力を持つことが多いです。
- ある製品仕様では、壁面に貼ることで「人が不快と感じる高い音(2,000〜5,000 Hz)の吸収率が 60〜80%程度に達する」旨が公表されています。
- 繊維/空隙構造によって共鳴吸音・摩擦損失型吸音が発生。吸音厚・密度・裏面空隙条件(裏張り空隙有/無)を設計変数として使うことができます。
- 樹脂パネル系の素材(発泡ポリエチレンやプラダンなど)と比べて、硬質フェルトは適度な空隙・内部拘束を持ちやすく、過度な響きや乱反響を抑えやすい性質を持つことがあります。
硬質フェルトボードの強み・メリット
実際に現場で使うとき、フェルトボードが持つ特徴(強み)がいくつかあります。以下、それらを整理します。
1. 反り・変形が少ない(寸法安定性)
- フェルト構造は繊維密度・接着安定性を確保すれば、気温・湿度変化の影響を受けにくく、反りが出にくい傾向があります。
- 特に屋内環境・乾燥環境では、プラスチック系素材で起こりやすい曲がりやそりを回避でき、外観や納まり精度が要求される場所で安心して使えます。
2. 環境配慮性・サステナブル性
- 再生繊維や回収 PET ボトル由来原料を一部使用する製品が増えており、環境負荷低減を訴求できる材料になります。
- 廃棄時には繊維系材として再リサイクル・焼却処理が比較的扱いやすく、樹脂発泡材などと比べて環境ゴミのインパクトを抑えられる可能性があります。
- 内装材・建築材のグリーン調達要件や環境認証(LEED や WELL 等)を検討する際、再生繊維素材と吸音性能を併せ持つフェルトボードは有利な選択肢となることがあります。
3. 加工性の良さ
硬質フェルトボードは、比較的加工適性が高い素材です。具体的には:
- プロッター切断:薄板であれば精密にパスカットが可能
- トムソン加工(打抜き):繊維板構造により抜き加工性も良好
- NC ルーター加工:孔あけ・溝加工が可能
- 貼り合わせ(ラミネート):表面にファブリックやフィルム材を貼る複合構成にも適応
- 固定施工:ビス打ち、ピン留め、接着剤固定がしやすい
- 印刷・意匠加工:シルク印刷、熱転写、インクジェット、箔押しなど、表面仕上げ加工が可能
こうした柔軟な加工性が、デザイン性を求める内装用途や見せ場のある場所で使いやすくしています。
4. 意匠性・デザイン性
- 厚み・カラー・模様・表情(凹凸・面取り)などにバリエーションを持たせやすい。
- 吸音性と意匠性が両立したパネルとして、壁掛けアートパネル・調音インテリアパーツとしても活用が進んでいます。
- 展示会などで目にする「形状を変えた吸音パネル」「幾何学パターンを施したフェルトボード」などは、この意匠性を生かした応用例と言えます。
デメリット・注意点・限界
一方で、硬質フェルトボードにも留意すべき点があります。以下、実務目線でのリスク・制限を挙げます。
1. 吸音限界・低域吸音の弱さ
- フェルトは繊維吸音型材であるため、低周波音(たとえば 100~500 Hz 領域)については厚みに依存します。薄板では十分に吸音できない可能性があります。
- 低域を補いたい場合、「裏空隙を確保する」「背面空隙層を設ける」「複合構造にする」など設計が必要です。
2. 耐久性・摩耗性・汚れ対応
- 繊維表面ゆえ、こすれ・摩耗・引っ掻きなどには弱い可能性があります。
- 汚れ・染み・ほこり付着のメンテナンス性を事前確認する必要があります(表面処理、クリーニング対応性など)。
- 長期間の曲げ・振動・衝撃負荷において繊維剥離や剥がれが起こる可能性があります。
3. 接着・固定の密着性
- 壁面や下地材との界面において、吸着が弱い・剥がれやすいケースが出ることがあります。下地材の材質・平滑性・面圧確保が重要です。
- 粘着シート貼り(両面テープ等)を使う場合、接着剤の耐久性・付着力・汚染性を確認する必要があります。
4. 吸音設計の難易度
- 吸音性能は密度・厚さ・空隙構造・裏空隙条件など設計の自由度が多いため、最適化を間違えると性能を十分発揮できない。
- 見た目重視でデザイン性を追うあまり、吸音特性が犠牲になることも。
5. 火災安全性・難燃性
- 吸音フェルトボードは繊維素材ゆえ、火災安全性・難燃性対応を考慮する必要があります。
- 表面抑制処理(難燃剤、耐火コート)を併用した製品が望まれます。
施工・取り付け実例と現場観察
私自身も施工現場に立つ機会が増えてきましたので、いくつかのポイントを現場視点で紹介します。
実施工例の概要
- 会議室・音響調整室:壁面吸音パネルとして硬質フェルトボードを施工
- オフィス・打合せスペース:パーテーションとして吸音パネルを壁代替的に使用
- 店舗・ショールーム:意匠性も重視しつつ吸音機能を持たせた壁面パネル
- 集中ブース/デスクトップパーティション:小規模ブースにフェルトボード材使用(例:Felmenon をベースにした卓上集中ブース)

現場で感じた効用と注意点
- 反りが出にくいため、隅部・コーナー納まりがきれいに出せる
- パネル同士の継ぎ目処理が重要。隙間ができると音漏れや断面反響が生じやすい
- 重ね貼りや切り抜き加工も現場で比較的容易。たとえばコンセント穴や配線孔なども容易に切り抜ける
- 釘打ち/ビス留めが有効。ただしネジが繊維を押し潰すような固定法は避けるべき
- 素材の加圧取り付け・接着剤補助・下地調整を行うことで、剥がれや浮きを防止できる

用途② 緩衝材・クッション材としての硬質フェルト
意外に知られていませんが、硬質フェルトは 緩衝材・クッション材 としても有効です。
- 発泡樹脂よりも「反発が穏やか」な衝撃吸収特性を持つ
- 寸法安定性が高いため、輸送中の隙間詰めや固定材に適している
- 高荷重下でも「へたり」が少なく、繰り返し緩衝に耐える
実例
- 精密機器輸送用の間仕切りやスペーサー
- 美術品やガラス製品の輸送用緩衝材
- 車両部品の組付け時の仮固定材
特に 発泡PEやウレタンでは反りや変形が出やすい 部分を、硬質フェルトで置き換えると安定性が増します。
用途③ コルク代替のピンボード・掲示板
従来、掲示板の定番素材といえば「コルク」でした。
しかし近年は、コルク供給の不安定さやコスト高騰から、硬質フェルトボードを代替として採用する例が増えています。
- 画鋲やピンの保持力が高い
- コルクよりも耐摩耗性が高く、長期間使ってもボロボロになりにくい
- カラーや意匠性が自由で、オフィス空間に調和しやすい
オフィスのパーテーション、学校の掲示板、工場の伝達板など、「見せる掲示板」 として相性の良い素材です。

用途④ 高機能繊維フェルト(ケブラー®・ザイロン®など)
吸音や内装用途とは別に、高耐熱・高強度フェルト の需要も拡大しています。
ケブラー®製フェルト(アラミド繊維系)
- 高強度・耐切創性・耐熱性に優れる
- 300℃以上の耐熱性を持つ製品も存在
- 精密機器や金属部品の高温搬送ラインで使用
- 耐摩耗性が高く、パッキンやライナー材に適用可能
ザイロン®製フェルト(ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール)
- 世界最高クラスの引張強度を持つ繊維
- 高温環境下でも寸法安定性が高い
- 電子機器・自動車・航空宇宙分野で採用実績あり
- 耐熱パッキン材や高荷重用の緩衝材として活用
これらは 一般的なPETフェルトとは一線を画す「産業資材フェルト」 と言えます。
メリットとデメリット(総合整理)
メリット
- 吸音・緩衝・断熱・掲示板など多用途対応
- 寸法安定性が高く、反りにくい
- 加工性が良く、打ち抜き・切削・印刷対応が可能(硬質フエルトボード)
- 廃棄繊維リサイクル品も多く、環境配慮性が高い
- コルクや発泡樹脂の代替として採用しやすい
デメリット
- 繊維素材のため摩耗や汚れに弱い
- 低周波音吸収は厚み依存(薄板では不得意)
- 樹脂発泡体に比べ、軽量性では劣る場合がある
- 難燃性は別途処理が必要な場合がある
- 高機能繊維フェルトはコストが高い
加工性・施工性のポイント
- プロッター・トムソン加工 → 精密な形状カットが可能
- NCルーター → 孔あけや溝加工に適する
- ビス留め・接着 → 下地次第で固定が容易
- 印刷・意匠加工 → 熱転写・インクジェット・箔押しなどに対応
「デザイン性+機能性」を同時に求められるシーンで優れています。
まとめ:吸音+緩衝+高機能で広がるフェルトの可能性
硬質フェルトボードは、吸音材として注目されがちですが、
- 精密機器輸送用の緩衝材
- コルク代替の掲示板
- 耐熱パッキンや高耐久部品用の高機能フェルト
といった多彩な用途で活躍できる素材です。
特に ケブラー®・ザイロン®といった高性能繊維フェルト は、製造業や輸送業の現場で「なくてはならない部材」になりつつあります。
今後は「環境対応」と「高機能化」を両立させた製品がさらに増えていくと予想されます。
設計・調達の現場では、吸音材としてだけでなく、緩衝・固定・耐熱・構造補助 といった観点でも「フェルト素材」を検討リストに加える価値があるでしょう。