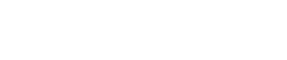熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂・エラストマーとは?ゴムはどの分類に入るのか
2025.09.02

樹脂やゴムといった高分子材料は、製品設計や部品調達において欠かせない存在です。しかし、「熱可塑性樹脂」「熱硬化性樹脂」「エラストマー」という言葉を聞いても、その違いをすぐに説明できる方は少ないのではないでしょうか。この記事では、これらの分類を整理し、さらに「ゴム」がどこに位置づけられるのかを詳しく解説します。
熱可塑性樹脂とは
熱可塑性樹脂とは、一度成形した後でも加熱すれば再び溶融し、冷却すると固まる特性を持つ樹脂です。
主な特徴は以下の通りです。
- リサイクル性が高い:再加熱して再成形が可能
- 加工性に優れる:射出成形や押出成形に適している
- 代表的な種類:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリカーボネート(PC)など
自動車部品や包装材、家電筐体など幅広い分野で活用されています。
熱硬化性樹脂とは
熱硬化性樹脂は、加熱すると化学反応により硬化し、一度硬化すると再加熱しても溶けない樹脂です。
特徴としては以下が挙げられます。
- 高い耐熱性・耐薬品性
- 寸法安定性に優れる
- 代表的な種類:フェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂など
電気・電子部品、接着剤、塗料、複合材料の母材として多く利用されます。
エラストマーとは
エラストマーとは、「弾性を持つ高分子材料」の総称です。
常温ではゴムのように伸縮性を持ち、外力を除くと元の形状に戻ります。
大きく以下の2種類に分類されます。
- 熱可塑性エラストマー(TPE)
- 熱可塑性樹脂のように加熱で軟化・再成形可能
- 代表例:スチレン系TPE(SBS, SEBS)、オレフィン系TPE、ポリエステル系TPE
- 熱硬化性エラストマー(架橋ゴム)
- 加硫(架橋)処理により弾性を固定
- 代表例:天然ゴム(NR)、EPDM、NBR、シリコーンゴム
ゴムはどの分類に入るのか?
「ゴム」は一般的に熱硬化性エラストマーに分類されます。
生ゴムの段階では柔らかい熱可塑性樹脂的な性質を持ちますが、加硫(硫黄架橋や有機過酸化物による架橋)を行うことで熱硬化性を獲得します。これにより、強い弾性・耐久性・耐熱性が付与され、工業用部品に適した性質を持つようになります。押出・切削・金型成型と幅広い製造方法に対応可能です。
一方で、再利用可能な熱可塑性エラストマー(TPE)も登場しており、従来の加硫ゴムと使い分けが進んでいます。弊社では押出材料として使用されるケースが非常に多く御座います。シート材やブロック材が無く、切削加工品や打ち抜き品はほとんど見かけません。
ゴムスポンジとの関わり
ゴムスポンジは、上記のエラストマー系材料を発泡させたものです。
- EPDMスポンジ:耐候性・耐オゾン性に優れる
- CRスポンジ(クロロプレン):耐油性・難燃性を持つ
- シリコーンスポンジ:耐熱性・食品適合性に強い
用途としては、自動車のシール材、家電の緩衝材、防水・防塵パッキン、断熱材など幅広く利用されています。
まとめ
- 熱可塑性樹脂:加熱で再成形できる、リサイクル可能
- 熱硬化性樹脂:一度硬化すると再成形不可、耐熱性・耐薬品性に優れる
- エラストマー:弾性を持つ高分子材料、ゴムは熱硬化性エラストマーに分類される
特に「ゴムスポンジ」はエラストマーの発泡体であり、用途に応じて素材選択が重要です。
購買・設計担当者の方にとって、こうした基礎的な分類を理解することで、より適切な材料選定やコストダウン検討につながります。
👉 「ゴムスポンジ調達ナビ」では、EPDM・CR・シリコーンなど多様なゴムスポンジの加工・調達に対応しています。用途に応じた素材提案も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。